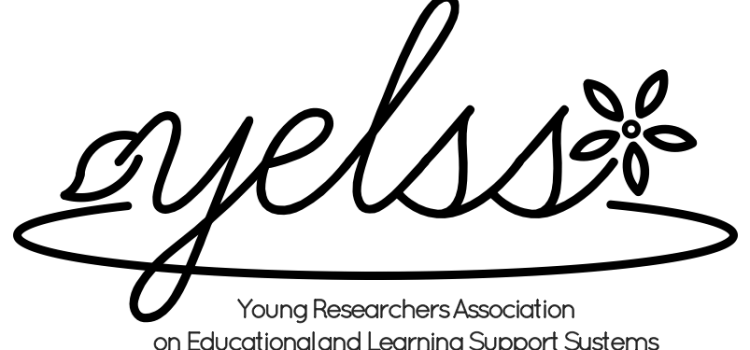こんにちは,M2の油谷です. 今年も教育・学習支援システム若手の会(Yelss)に参加させていただいたので,報告をば. Yelssは,その名の通り, 教育および学習支援を目掛けた計算機システム関連研究に携わる若手研究者が集まり, 連日朝から晩まで議論を交わす,今年で29回目(29年目)を迎えるアツい集まりです. 特に昨年度から,正式名称を「教育システム若手の会」から 「教育・学習支援システム若手の会」に変更するとともに, その運営方針も大きく舵を切り出しているようです. 2年前までの雰囲気は, 修士の学生や若手の先生方を中心として, 僕たちの研究分野についての理解を深めるような議論を通じて, ソーシャライズの場を提供してくれているような感じでした. 一方で,昨年からは,博士後期課程の学生を中心にガチな議論を交わしながら, 研究者の素養を養うような雰囲気へと変わっている印象です. そんなYelss,今年は11月16日(金)〜11月18日(日)で, 僕らにとっては近場の大阪(舞洲)開催で, 弊ラボからは,林先生,エマさん,僕(油谷)の3人が参戦でした. 今回は特に昨年までとはうって変わり, 学生も,修士・博士がグループを作り, 事前に十分に準備してきたプレゼンでパネルディスカッションのような企画がありました. 修士のテーマは, 「教育・学習支援システム研究における学士・修士の研究の違いとは」というものでした. (ちなみに博士はここに「博士の違い」が入ったものでした) 修士・博士2チーム各3人ずつで, この日に至るまでに密に議論して臨みました. 詳細は後述しますが,事前にいろいろと考えていた分, 当日はより深いことや別の視点から考えられ, とても有意義な時間になっていたように感じます. 総参加者数は,おそらく18名(教員10名・博士3名・修士5名)でした. では,大まかなスケジュール感と,感想をどうぞ. ============================================== 1日目は,金曜日の夕方頃から始まり, 自己紹介を含めたアイスブレーキングセッションがメインでした. 会場はこんな感じ 自己紹介はライトニングトークで一人3分で研究紹介です. (林先生のLT) 僕は3年連続で参加させていただいていることもあり, おおよその方はすでに存じ上げていましたが, 「研究内容」となると詳しくは知らなかったな,的な所感でした. この後は,お酒を交えてじっくり議論した後,
Yelss2018 MaiMai